イベント告知・レポート
IPO経験者に聞く、AIスタートアップがとるべき知財戦略とは「スモールビジネスから目指せるスタートアップ、IPOへの道 by IP BASE in 熊本」イベントレポート

2024年12月18日、特許庁スタートアップ支援班は、ネットワーキングイベント「スモールビジネスから目指せるスタートアップ、IPOへの道 by IP BASE in 熊本」を熊本市のスタートアップ支援施設「XOSS POINT.」にて開催した。イベントでは、23歳で起業し、IPOを果たした経験をもつ現マネックスグループ取締役兼執行役の山田尚史氏による講演と、九州を中心に知財支援に取り組むソシデア知的財産事務所の代表弁理士 小木智彦氏による講演、また、シード・アーリー期に必要なスタートアップ支援をテーマにしたパネルディスカッションが実施された。
冒頭では、熊本市 起業・新産業支援課 主事の姫野寛司氏が登壇し、熊本市のベンチャー・スタートアップ支援の取り組みを紹介した。

熊本市では、今回の会場となった「XOSS POINT.」を中心に「熊本版スタートアップエコシステム」の構築を目指し、起業家・支援者コミュニティの構築や、起業家の発掘・育成、産官学の連携などに取り組んでいる。「XOSS POINT.」は、令和4年度に開設された熊本市初のスタートアップ支援施設。令和5年度は年間364回実施したセミナーにのべ4864名が参加し、起業家コミュニティの形成を図っている。
起業家の発掘・育成プログラムとしては、高校生・大学生を対象とした「肥後創成塾」、アクセラレーションプログラム「HIGO CANVAS」、ピッチイベント「Kumamoto City Pitch」などを実施。また、実証実験をしたいスタートアップに対して熊本市が実証フィールド・情報の提供や広報協力をする「XOSS INNOVATION KUMAMOTO」を実施。さらに、民間企業とも連携し、販路の拡大や資金調達支援に取り組んでいるそうだ。
東大発AIスタートアップから学ぶ、成長の壁と上場のメリット
マネックスグループ取締役兼執行役の山田尚史氏は、「23歳での起業からIPO、経営の軌跡」と題し、東大発AIスタートアップPKSHA Technologyの起業から上場に至るまでの経緯と上場後の変化、AIがビジネスに与える影響について語った。
山田氏は2012年、23歳でPKSHA Technologyを創業。AI搭載型SaaSである「AI SaaS」を主軸に事業を展開し、2017年に東証マザーズに上場している。創業当時、深層学習技術はアカデミアに登場したばかりで市場がない状態だったという。これから成長が見込める市場に先んじて起業すると、時流に乗って売り上げは伸びた。また成長産業にはプレイヤーが多く集まるが、AIのように技術的な難易度が高い領域はそれ自体が参入障壁になり、スタートアップの優位性を保ちやすい。加えて、AIは応用領域が広く、あらゆる領域の課題解決に利用できるのも強みとなっている。
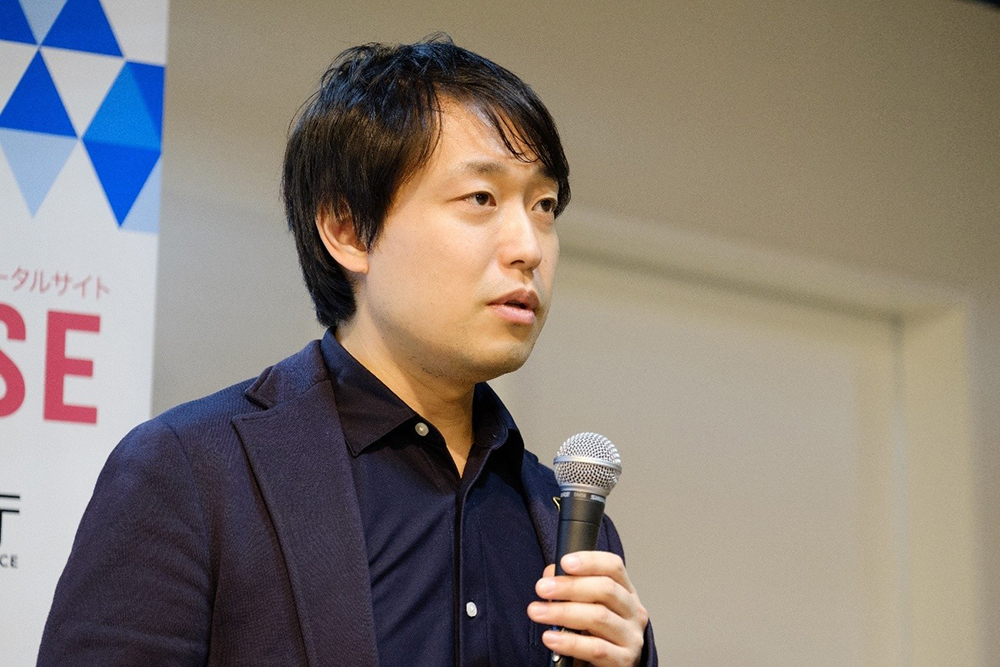
しかし、成長するほど組織の統制が難しくなる。同社では、社員が30人のときに、ミッション・ビジョン・バリューを言語化。50人でマネージャーを設置するなど、大きな組織変更を実施している。また、同社はエンジニア比率が60%以上と高いことも特徴だが、エンジニア中心の組織の場合、営業のように売り上げ効果を定量評価が難しいことや、エンジニアは管理職を嫌がる、といったチーム作りの苦労もあるようだ。組織づくりの課題を克服するためには、ミッションとビジョンで人を惹きつけることと、バリューとして自分たちの価値観や望ましい行動を規定し、意思決定の規範を示すことが重要だそう。
次に、上場について解説。上場は株式を一般の投資家に公開することで、資本の調達やブランド・信用力を向上できるのがメリットだ。また、創業初期のスタートアップの場合、報酬の一部をストックオプション(SO)で渡すことも多い。メンバーが成果を出すほど企業価値が上がり、自分の利益も増えるというインセンティブになり、優秀な人材の獲得にもつながる。ただし、ファイナンスは後戻りができず、特に株式の扱いは難しい。ファイナンスについては、積極的に情報収集し、客観的な第三者にアドバイスを求めることを勧めた。
最後に、AI時代のビジネスについて提言した。山田氏は、数年から数十年以内にはAI と無関係に生きることは不可能な時代が到来すると予測している。特に、知的労働や文字ベースの業務など、AI導入によるコストパフォーマンスが高い高所得者の仕事は、AIによって効率化されやすい。AIが当たり前の世界では、AIを事業に応用するための知識や、さらにそれを自分で作る能力がますます重要になるだろう。
スタートアップのステージ別、知財戦略のポイント
弁理士法人 ソシデア知的財産事務所 代表弁理士 小木智彦氏は、「ゼロイチ・1-10フェーズで知っておきたい知財戦略」と題して、スタートアップの各成長ステージで取り組むべき知財戦略を説明した。
スタートアップの成長は、シード期のアイデア段階から始まり、アーリー期でプロトタイプを作成し、ミドル期で最初のマネタイズと大きな契約を目指す。レイター期では市場を確立し、IPOに至ることが理想的だ。知財戦略としては、シード期で最初の特許出願、アーリー期でクリアランスと特許網の形成を行う。ミドル期で商標対策を実施し、レイター期で強力な特許出願を進める。これにより、成長の各段階で知財の保護と活用を図る。

小木氏は、知財戦略で押さえるべきポイントとして、1)オープンイノベーション等で連携する場合は、他社にアイデアを話す前に特許出願をすること、2)企業等との連携では知財の扱いを契約で縛ること、3)IPO時の時価総額を上げるには、ミドル期までに特許網を形成すること――の3つを挙げた。また、特許は新規性を失うと取得できないため、他人にアイデアを説明する前に出願しておきたい。遅くとも、アイデアをWebページでの発表やイベントへ出展、オープンイノベーション企画への応募の前には出願しておくのが原則だ。
事業によっては、特許出願しなくてもいいケースがある。特許出願すべきかどうかは、アイデアが公開されてもすぐに事業を模倣できるかどうかが判断基準になる。DX系スタートアップの場合、アルゴリズムは外部から見えないので模倣しにくいと考え、特許は不要と判断しがちだ。しかし、異なるアルゴリズムで同じサービスを始められる可能性があるため、ビジネスモデル特許などによる模倣対策も検討すべきだろう。
特許クリアランスは、専門家に依頼すると費用がかかるが、自社の事業に関連した特許分類を決めれば、自分自身で調査することも可能だ。また、製品化する際のネーミングやロゴは、必ず商標調査をして出願しておきたい。契約については、共同研究開発など他企業との連携する際には、アイデア送出時の知財の扱いを事前に決めておくことが大事だ。IPOやM&Aを目指すのであれば、早い段階から弁理士と相談し、日常的に知財業務を企業活動に取り入れておくことが望ましい。
経済学博士の梅澤伸嘉氏によるマーケティングのCP理論(C:コンセプト、P:パフォーマンス)によれば、売れる商品とは「買う前に、ほしいと思わせる力が強く、かつ買った後も、買ってよかったと思わせる力が強い」と定義されている。売る前に欲しいと思わせるのが「コンセプト」であり、これを守るのが商標権と意匠権だ。一方、購入後に満足度を与える「パフォーマンス」としての商品機能は特許権で保護される。小木氏は、「スタートアップの場合は、特にパフォーマンスが得意であり、市場が確立するにしたがってコンセプトも意識することが大事」と説明した。
特許庁・INPITのスタートアップ支援施策
特許庁の講演では、「特許庁・INPITのスタートアップ支援施策」と題して、1)知財ポータルサイト「IP BASE」を通じた情報発信・コミュニティ活動支援、2)INPITの相談窓口、3)知財専門家を派遣する伴走支援プログラム、4)料金減免、スーパー早期審査などの支援制度について紹介した。

AIスタートアップのオープンイノベーションにおける知財と契約のポイント
パネルディスカッションには、講演で登壇した山田氏と小木氏、関口氏に加えて、熊本市経済観光局 産業部 起業・新産業支援課の野口信太朗氏が参加し、山田氏の経験から、AIのオープンイノベーションにおける知財戦略について話し合った。
PKSHA Technologyの創業当初は、単独での特許は少なく、企業との共同研究で共同出願する形でいくつかの特許を出願していたとのこと。AIのオープンイノベーションでは、基本モデルをスタートアップが作り、大企業がビッグデータを使ってアプリケーションを開発する、というケースが多く、AIモデルの権利の所在や著作権管理が問題になることがある。PKSHA Technology社の場合、山田氏が弁理士としての知見を活かして契約内容と製品の提供形態を工夫していたため、事業成長の妨げにはならなかったそうだ。AIのオープンイノベーションは、個別のケースによって留意すべき契約条件は異なる。特許庁の「オープンイノベーションポータルサイト」には「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(AI編)」が公開されているので、契約時の参考にしていただきたい。





