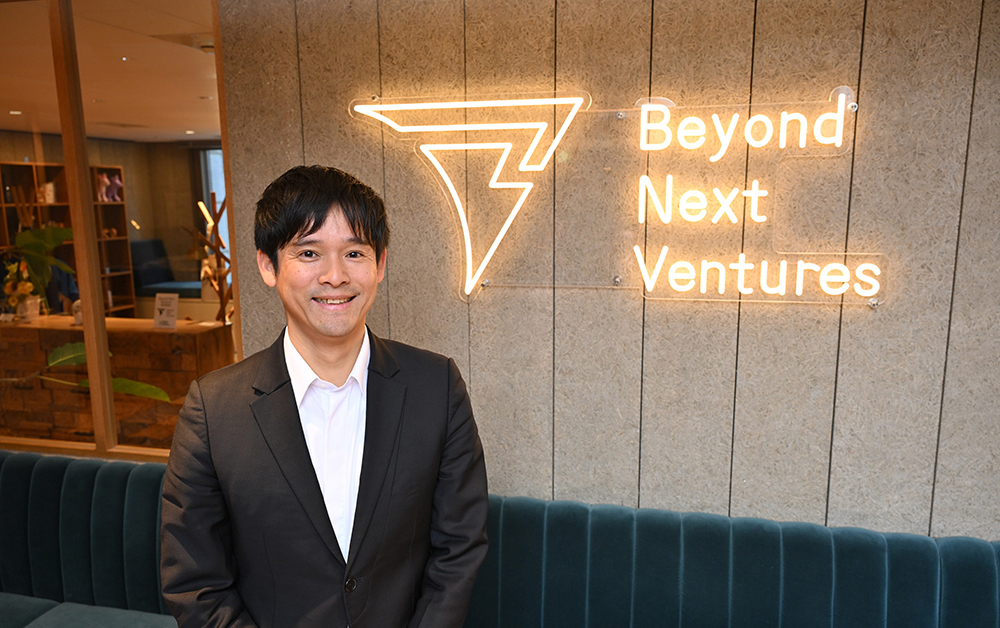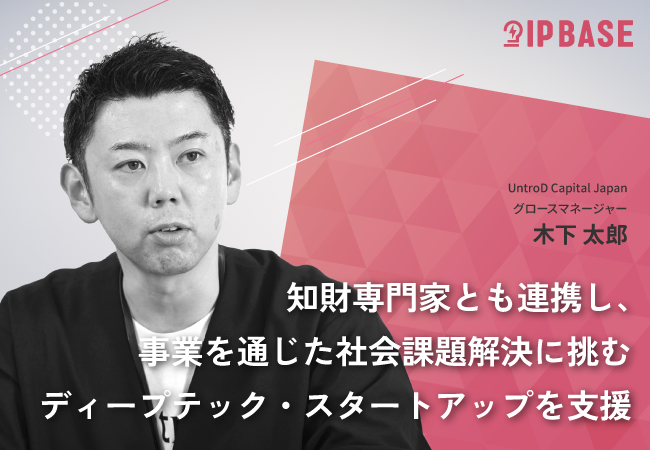スタートアップエコシステムと知財
Beyond Next Ventures 株式会社 代表取締役社長 伊藤 毅氏インタビュー
日・印に拠点を置き、資金と人材の両面からディープテック・スタートアップのエコシステム発展を支援
Beyond Next Ventures 株式会社は、日本とインドを拠点にディープテック領域に投資するベンチャーキャピタルだ。2014年の設立以来、ディープテック・スタートアップのエコシステム発展を目指し、資金と人材の両輪での支援に取り組んでいる。代表取締役社長 伊藤毅氏に、同社の取り組みやディープテックの今後の展望について伺った。

Beyond Next Ventures 株式会社 代表取締役社長
伊藤 毅(いとう・つよし)氏
東京工業大学大学院 理工学研究科化学工学専攻修了。2003年4月にジャフコ(現ジャフコ グループ)に入社。Spiberやサイバーダインをはじめとする多数の大学発技術シーズの事業化支援・投資活動をリード。2014年8月、研究成果の商業化によりアカデミアに資金が循環する社会の実現のため、Beyond Next Ventures 株式会社を創業。創業初期からの資金提供に加え、成長を底上げするエコシステムの構築に従事。出資先の複数の社外取締役および名古屋大学客員准教授・広島大学客員教授を兼務。
内閣府・各省庁のスタートアップ関連委員メンバーや審査員等を歴任。
ディープテック・スタートアップの資金と人材を両輪で支援
Beyond Next Ventures 株式会社は2014年8月に創業し、日本とインドでスタートアップ投資を手掛けている。同社は2015年に1号ファンドを組成し、主に国内の大学発ベンチャーに注力したVCファンドとして投資を開始した。現在、3つのファンドを基幹とし、2024年7月に257億円でクローズした3号ファンドは、ディープテック特化のファンドとして国内有数の規模を誇る。

伊藤氏は前職で大学発ベンチャー向け投資チームのリーダーを務めた経験が創業のきっかけになったと語る。「当時は、大学発ベンチャーへの投資はマイナーな分野でした。花形だったインターネットサービス関連の部門からの異動だったので、正直残念に思っていました。それでも、今後はディープテック・スタートアップがきっと伸びてくるにちがいないと思い、そこからこの分野にのめり込んでいきました」と伊藤氏は振り返る。
そうした中で、日本の研究機関には研究資金が投資されている一方、社会実装が弱いという課題を感じていたという。伊藤氏は、「この状況が続くと、日本のアカデミアへの投資は先細ってしまう。我々が大学発ベンチャーへの投資を通じて成功事例を積み重ねることで、日本のアカデミアにもっと資金を循環させることができるはずだと考え、Beyond Next Venturesをスタートしました」と創業理由を説明する。
同社は、業界の中でもいち早く大学発ベンチャー支援の必要性に注目し、スタートアップ投資とエコシステム構築の両輪で活動してきた。2016年には、ディープテック特化のアクセラレーションプログラム「BRAVE」を開始。スタートアップに対して、キャピタリストや専門家によるメンタリングのほか、経営人材のマッチング機会を提供している。さらに、2017年には、経営者不足の課題解決を目的とした起業家/社内起業家育成プログラム「INNOVATION LEADERS PROGRAM」の運営開始、2019年にはバイオベンチャー向けのシェアラボ「Beyond BioLAB TOKYO」を東京・日本橋に開設するなど活動の幅を広げている。
伊藤氏が感じてきたディープテック・スタートアップの課題は、経営人材の不足だという。「経営者がいれば、大学の先生方が研究のかたわらで無理をして起業しなくても、VCから資金を調達できたのに、と思うケースが多々ありました。我々が起業前から支援し、シード期から経営者を入れることができれば、事業の成功確率が上がるのではないかと考えていました」と伊藤氏。そこで大学発スタートアップへ経営人材を供給するために、東京海上日動キャリアサービスで大学発ベンチャー専門の経営人材支援を手掛けていた鷺山昌多氏を同社に迎え、2017年にはVCとして初の有料職業紹介事業の許認可を取得した。
「BRAVE」にはこれまで180チームが採択され、起業前に参加した123チームのうち59社が起業。累計資金調達額は約500億円にのぼるとのこと。さらに、参加チームに対して550名以上の経営者人材をマッチングしており、卒業生たちのネットワークも形成されているという。
投資領域を拡大するとともに、インドにも拠点を設置

現在、同社の投資領域は、1号、2号ファンドの「医療・医療ヘルスケア」、「創薬・バイオ、アグリ・フード」に加え、3号ファンドでは「デジタル・宇宙」と「クライメートテック」もカバーしている。これら2つの領域は規模が大きく、相応の資金力やアセットを必要とする。そこで3号ファンドは従来よりも期限を1年長く設定し、さらに1社あたりの累積投資額を最大20億円に引き上げた。
伊藤氏は「最大20億円のシード投資が可能なディープテック特化のファンドは少ない。当社がこの領域を牽引していくべきだと考えています。その結果、黒字化まで数百億円調達する必要があるディープテックの領域にも投資を行えるようになっています」と語る。
昨今は世界的にディープテック投資が注目されており、政府の補助金や各国の基金から資金が投下されている。これらと民間のエクイティとを組み合わせることで、事業の成功確率が高まりそうだ。
伊藤氏が投資先の中で注目している分野のひとつに宇宙があるそうだ。「2030年に国際宇宙ステーション(ISS)の運用が終了しますが、日本としてはISSにある実験棟「きぼう」のような施設を民営で設置することも検討しているようです。米国で始まった宇宙産業の民営化の流れが日本でも始まっています」と伊藤氏。また、量子コンピューターの領域についても「次世代コンピューターとして間違いなく確立されていく分野」と注目しているという。
Beyond Next Venturesは2019年にインドのベンガルールに拠点を設置し、インドのスタートアップへの投資と日本企業のインドにおける新規事業創出を支援している。インドに拠点を構えた理由について伺った。
「2号ファンドを組成した際、日本に留まらず海外で活動できる投資会社を目指し、その20%を海外投資に充てることを決めました。海外拠点をどこにするかを考えたところ、中国やアメリカは規模が大きすぎるし、東南アジアは地域ごとに特性が異なり、我々のリソースでは難しい。一方、インドの市場は中国に次ぐ規模があり、若い世代の人口も多く活気がある。海外に行くならインドだと直感しました」と伊藤氏。
拠点を設置した当時のインドはIT関連のデジタル投資が中心で、15年前の日本の状況に似ていたという。それが最近ではインドでもディープテックが盛り上がりを見せてきており、現地のVCも少しずつ増えているそうだ。
ディープテック投資における知的財産の重要性

ディープテック投資において知的財産は極めて重要だ。大学で研究された成果を技術移転し、事業化できる体制をつくるには知的財産がその価値の源泉となるからだ。しかし、大学での特許出願は内容がニッチになりやすく、事業化をあまり念頭に置いていないケースもみられるという。
同社では、投資先の知財強化のため、創業前の段階から弁理士や弁護士といった専門家を紹介するなど、知財戦略の構築を支援している。また、「BRAVE」プログラムで知財専門家による講演を開催するなど、啓蒙活動にも力を入れているそうだ。
ディープテック領域の知財戦略のポイントとして、「材料や創薬分野は特許が極めて重要なので、創業初期から意識して取り組む必要があります。一方で、ハードウェア系は、プロセス技術などは権利化せずにブラックボックスにしたほうがいい場合もあります。また、リバースエンジニアリングで回避されやすいものは広範囲に押さえたり、競合が次に押さえそうな領域の特許を先に押さえる、といった戦略も有効でしょう」と伊藤氏。
コアとなる強力な特許を取得できればいいが、そうでない場合は複数の知財を確保する必要があり、多額の費用がかかる。以前は資金の問題から知財をあきらめていたディープテック・スタートアップも少なくなかったが、最近では多額の資金調達を得て、大企業と同等の知財戦略を組むスタートアップも出てきているという。
最後に、これからディープテック・スタートアップを取り巻く環境はどのように変化していくだろうか。伊藤氏に意見を伺った。
「ひとつは、VCのファンドサイズの大型化に伴い、これまでのようなスモールIPOではなく、よりスケーラブルなビジネスを目指すフェーズに入ります。その結果、ディープテック・スタートアップは必然的に海外に出ざるを得なくなり、創業初期から海外市場に進出するスタートアップが増えるでしょう。
もうひとつは、ディープテック投資の増加による影響です。今の状況を農業に例えるなら、苗を植えて育ったら全部刈り取るということを続けており、土壌環境はどんどん悪化しています。研究者が減り、創薬分野はすでに空洞化が始まっています。これが今後のディープテック投資にどのような影響を及ぼすのか。我々もこの事業を継続するには、土壌をあらためて整えることを意識して取り組まなければなりません。これはディープテックに限らず、日本全体の課題として考えていくべきです」(伊藤氏)