イベント告知・レポート
スタートアップが留意すべき契約に関する課題と「OIモデル契約書」の活かし方とは 「スタートアップが経験しがちな契約をめぐるトラブルと、その解決策のヒント」レポート
スタートアップ向け知財戦略ポータルサイト「IP BASE」を展開する特許庁スタートアップ支援班は2025年2月7日に、一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J)とともに、知財イベント「スタートアップが経験しがちな契約をめぐるトラブルと、その解決策のヒント」を、日本橋ライフサイエンスビルディングで開催した(オンライン同時開催)。同イベントでは、特許庁が作成した「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(OIモデル契約書)」とそのポイントをまとめたマナーブックの紹介や、ライフサイエンス分野におけるスタートアップと事業会社/大学間の知財契約をテーマとするパネルディスカッションが行われた。

オープンイノベーション促進のための「OIモデル契約書」とは
イベントの前半では、「改めて『オープンイノベーション促進のためのモデル契約書』とは?」と題して、特許庁総務部企画調査課の新里太郎氏が「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(以下、OIモデル契約書)」と、その解説パンフレット、マナーブックについて紹介した。

「OIモデル契約書」は、2020年度の公正取引委員会による「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書」を受け、大企業とスタートアップ企業の契約の適正化を図るために「スタートアップとの事業連携に関する指針」(公正取引委員会・経済産業省)の付属文書として作成されたものだ。
「OIモデル契約書」の特徴は、契約書のひな形ではなく、実際の交渉シーンについてロールプレイ形式で解説している点だ。事業会社とスタートアップのオープンイノベーションを想定した「新素材編」「AI編」、大学と事業会社、大学と大学発ベンチャーを想定した「大学編」があり、それぞれに共同研究開発契約書やPoC契約書、ライセンス契約書といった各種契約書の例が示されている。
また、オープンイノベーションに関わる人向けに、交渉の流れやポイントをイラストでわかりやすく解説したパンフレット、さらに入門編として、良好な関係構築のために意識すべきポイントをまとめたマナーブックも公表されている。なお、これらはすべてオープンイノベーションポータルサイトに公開されており、誰もが参照できる。
研究者と経営者の契約や知財の考え方のギャップをどう埋めるか
後半のパネルディスカッションでは、株式会社メトセラ 取締役COO 事業推進部長の菅愛子氏、C4U株式会社 代表取締役社長・弁護士の平井昭光氏、STORIA法律事務所パートナー弁護士の柿沼太一氏、特許庁総務部企画調査課 活用企画係長の新里太郎氏が登壇し、辻丸国際特許事務所 代表弁理士の辻丸光一郎氏をモデレーターとして、スタートアップが遭遇しがちな契約に関するトラブルや「OIモデル契約書」の活用をテーマに話し合った。

「OIモデル契約書」は、公正取引委員会の調査報告を受けて、スタートアップが大企業との連携で不利な契約を結ばないようにするために作成されたものだ。「報告によれば、大企業との連携で約2割のスタートアップが不利な契約を提示された経験があり、その中でも知財担当者がいないスタートアップは特に不利な契約を結んでしまっているケースがある」と特許庁の新里氏は説明する。
「OIモデル契約書」の策定に携わった柿沼氏は、「契約内容が明らかに不利な内容であっても、体制が整っておらず立場も弱いスタートアップではその内容を覆すことは難しい。この現実を踏まえ、実務に役立つツールとして『OIモデル契約書』を活用してほしい」と述べた。
平井氏は大企業との共同研究における契約について、研究計画の内容や研究分担はフェアだが、経済条件やビジネスタームに問題があることを指摘する。また、菅氏は、共同研究において「研究者同士では盛り上がるが、誰が資金を出すのか、どのような成果が期待されるのかなど詳細が曖昧なまま進んでしまうことがある。ビジネスサイドとしては、研究者の思いを大事にしながら、契約内容や今後の発展にどうつなげていくかを考えなければならない」と研究者と経営側のコミュニケーションにおける課題を挙げた。
柿沼氏はディープテックの課題として、研究者と経営者間での特許出願に関する考え方のギャップや、その調整の困難さを指摘。「OIモデル契約書」がこれらの問題を必ずしも完全に解決するわけではないが、社内で契約や知財の考え方をすり合わせるためのツールとしても役立つのではないかと提案した。
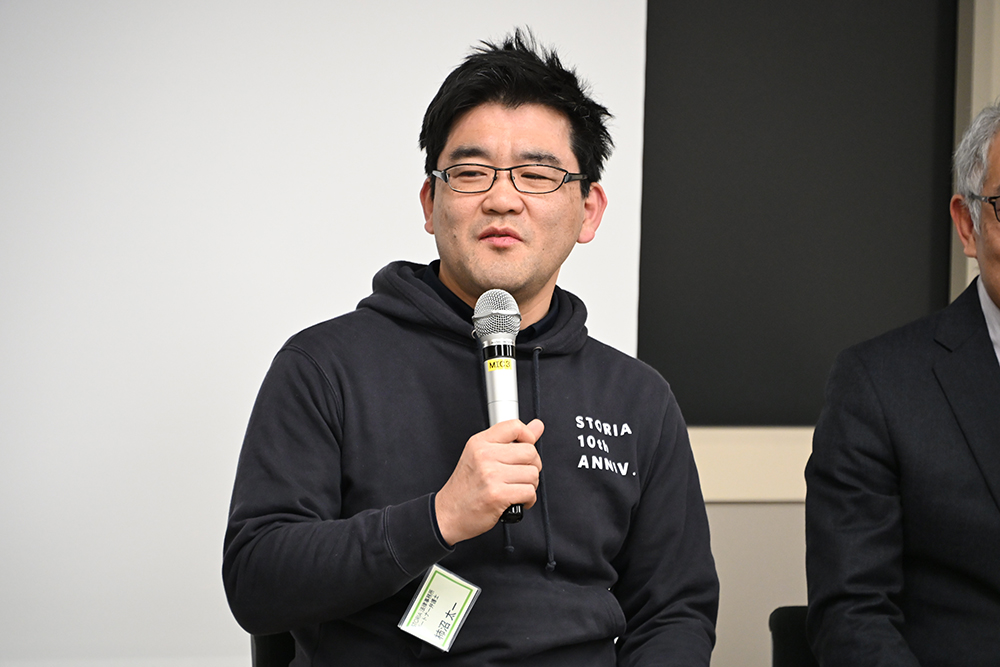
共同研究における知財単独出願、ライセンス契約の課題
共同研究では、契約終了後に研究内容に関する発明が単独出願されてトラブルになることも少なくないという。柿沼氏は、「契約書で単独発明と共同研究の出願の扱いについて明記していても、技術認定の問題がトラブルの原因になる」と指摘。共同研究における研究管理の重要性を強調した。
菅氏は、製薬会社におけるバリュエーションチームでの経験から、「アセットの価値を決める際にアップフロントとマイルストーンの区分が重要だが、スタートアップはその区別が曖昧になってしまいがち」と話す。平井氏はその理由として、スタートアップは将来収益やそれに基づくディスカウント・キャッシュフロー、その結果としての現在利益を示すことが難しいため、アーリーディスカウントされやすいことを指摘する。
ライフサイエンス分野特有の問題として、開発期間が長いため、ロイヤリティよりも先に資金を得ることが重要になる。そのため、製薬業界の契約ではステージゲートを設定して期間を決めるまではマイルストーンがよく使われる。平井氏は、「ライフサイエンスではMTA契約や共同研究の段階では経済的リターンが低いが、動物実験でPoCが得られた後であれば良い条件が得られるだろう」と述べた。

日本企業、海外企業との契約の違い
平井氏によると、欧米では契約書に書かれていないことは認められないため、契約書はかなり分厚くなるという。対して、日本では契約書には書かれていないことも多く、定期的に研究開発会議などでコミュニケーションを図りながら補完することが一般的だ。さらに平井氏は、「研究の成果やアイデアを出すと、相手がそれを利用しようとする『陣取り合戦』の感覚が常にある」と述べる。
柿沼氏は、「日本は契約書に書いていないことは法律が適用されるということでそこまで書き込まない。海外との契約では、どの法律が適用されるか、どう解釈されるのかわからないので、余白を出さないという考え方が取られる」と前提の違いを説明した。
菅氏は、バックグラウンドIPに関する海外との交渉の難しさについて述べた。受託契約でのフィーの設定やロイヤリティに関する問題があり、交渉で困難を感じたという。柿沼氏も「バックグラウンドIPの処理は明確にしないと予想外の問題が生じる」と指摘する。辻丸氏は、「海外との契約ではバックグラウンドIPがよく問題になることを意識しつつも、できないことは断るべき」とし、「日本企業同士の契約はWin-Winの関係を前提にしているが、海外との契約では異なる文化が影響する」と述べた。
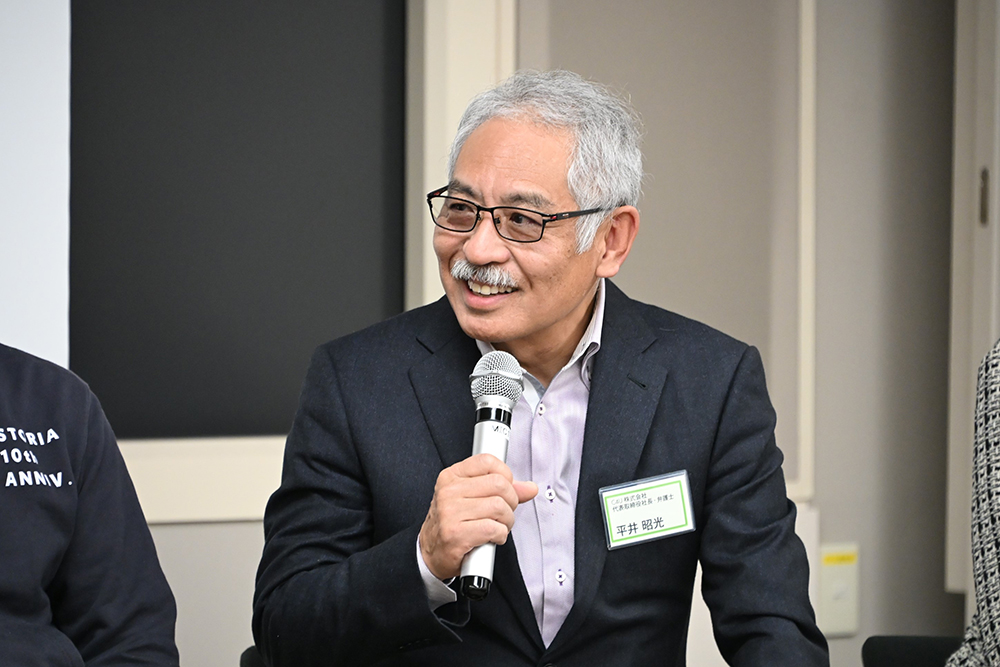
最後にパネリストたちからひと言ずつ、「OIモデル契約書」の活用についてコメントした。
菅氏:スタートアップに参画するまでは契約書や知財に関してそれほど詳しくなかったのですが、メトセラに入社してから弁護士・弁理士の先生とお話をしながら学んできました。今回作成された「OIモデル契約書」やマナーブックは、実際の場面を想起しやすく非常にありがたかったです。ぜひみなさんにも活用していただければと思います。
平井氏:契約も特許も知財も、どれも非常に重要です。その中で公正取引委員会や特許庁が協力して良いツールを作ってくれたのはとてもうれしい。我々もこれを活かせるようにがんばっていきたい。
柿沼氏:作成に関与した者として「OIモデル契約書」には思い入れもあります。ビジネスや技術に比べれば、法律はそれほど難しくないと思います。技術者の方なら、時間を取って通読いただければすぐに理解できると思いますので、ぜひお読みください。
新里氏:オープンイノベーションに取り組むにあたって、つまずいたり、うまくいかなかったりしたときに「OIモデル契約書」を思い出して、参照していただければ幸いです。
辻丸氏:「OIモデル契約書」が公開されるまでは誰もが参考にできるものがあまりなかった。標準的な参考資料ができたことは重要です。経営に関わる方だけでなく研究者や技術者の方も、一度目を通していただければと思います。

文●松下典子 編集●ガチ鈴木(ASCII STARTUP) 撮影●曽根田元




