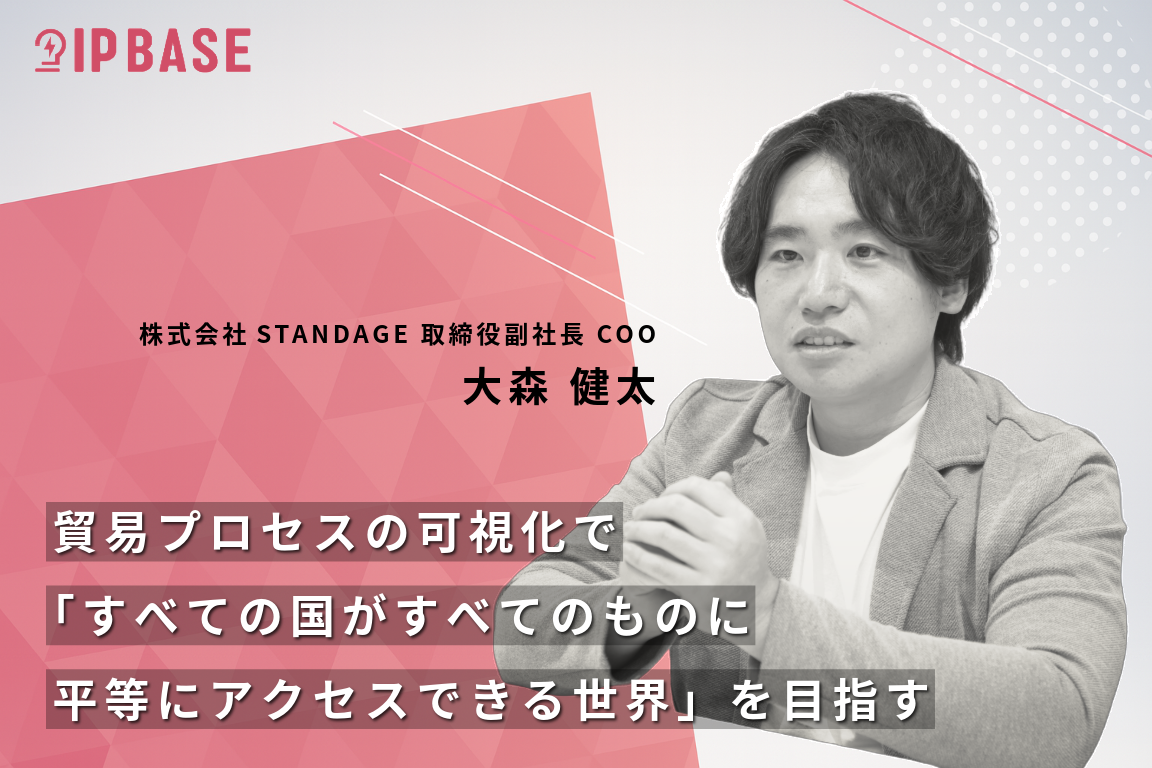CEOが語る知財
株式会社Helical Fusion 代表取締役CEO 田口昂哉氏インタビュー
核融合発電を「研究」から「実装」へ 商用化への最短距離を描く
核融合発電の実用化は、長年「夢のエネルギー」と呼ばれてきた。CO₂を排出せず、燃料制約も小さい次世代電源として期待される一方、研究段階にとどまり続けてきたのも事実である。そうした中、核融合を“研究テーマ”ではなく“発電事業”として成立させることに真正面から向き合っているのが、株式会社Helical Fusionだ。IPAS(知財アクセラレーションプログラム)では、事業化が進む一方で未整理だった知財戦略を経営と一体で再構築した。代表取締役CEOの田口昂哉氏に、事業の現在地と、その裏側にある判断軸を聞いた。

株式会社Helical Fusion 代表取締役CEO
田口昂哉(たぐち・たかや)氏
京都大学大学院文学研究科(倫理学)修了。みずほ銀行、国際協力銀行(JBIC)、PwCアドバイザリー(M&A)、第一生命、スタートアップCOOなどを経て株式会社Helical Fusionを共同創業。
核融合発電の「商用化」を見据えた事業設計
核融合発電は、将来のエネルギー源として長年研究されてきた技術である。燃料1gから石油8t(タンクローリー1台分)に値する莫大なエネルギーを生み出せる一方で、発電時にCO₂を排出せず、燃料となる資源の制約が小さいことから、環境負荷の低いエネルギーとして期待されてきた。そして、天候に左右されず安定的に電力を供給できることから、いわゆるベースロード電源を担える可能性がある。
一方で、核融合は「研究としては成立しているが、発電事業としては遠い」というイメージを持たれやすい分野でもあった。実験装置でエネルギーを生み出すことと、社会に電力を供給する発電所として成立させることの間には、大きな隔たりがあるからだ。
Helical Fusionは、こうした核融合分野において、最初から発電を行う事業として成立させることを目的に設立された企業である。採用しているのは、ヘリカル型と呼ばれる核融合方式で、理論的にプラズマを安定的に閉じ込めやすく、長時間運転に適しているとされてきた方式だ。日本では国主導の研究開発によって長年知見が蓄積されており、Helical Fusionはその成果を前提に、発電装置の実装を目指している。
同社のスタンスを特徴づけているのは、「研究」を「実用発電」に持っていくという明確なゴールに据えている点である。田口氏は、商用発電所として成立するための条件として、次の三つを挙げている。
第一が「定常運転」であり、一年を通して安定的に稼働し続けられることを指す。瞬間的に核融合反応が起きても、長期間にわたって運転できなければ発電所とは言えない。第二が「正味発電」で、発電のために投入するエネルギーを上回り、発電所の外部に十分な量の電力を取り出せることが求められる。そして第三が「保守性」だ。運転後の機器交換やメンテナンスを、現実的な時間とコストで行えなければ、商用発電所として継続的に運用することはできない。
「定常運転、正味電力、保守性。我々はこの三つが最低限必要であると考えており、今の段階でも実現の目処が立っているというのがヘリカル方式の強みです。ありがたいことに、周囲の方々にヘリカル方式について説明をすると、『ヘリカル方式が一番良さそうですね』と言っていただけます。一般の方にも受け入れていただけるという手応えを感じています」(田口氏)
Helical Fusionは、この三要素を満たすかどうかを判断軸に据え、技術や開発テーマを選び取ってきた。論文成果や瞬間的な実験成功を目的とするのではなく、発電所として運転し続けられるかという視点から、事業全体を設計している点に同社の立ち位置がある。
「実用発電」へのロードマップとHelical Fusionの現在地
核融合発電に至るまでの道筋は、決して一足飛びではない。Helical Fusionが描く核融合発電への道筋は、「Helix Program」としてロードマップに整理されている。最終到達点は、最初の発電装置である「Helix KANATA」による定常&正味発電だ。

2030年代に「実用発電」を行う世界で唯一の開発計画「Helix Program」
田口氏によれば、開発の歴史の中で最も時間を要したのは、ヘリックス計画の前の概念実証、高温プラズマの実現(1億度)、プラズマ定常運転(約1時間)といった、基礎研究に近い領域である。これらは技術的不確実性が極めて高く、民間企業が単独でリスクを取ることが難しい。日本では、核融合科学研究所など、公的研究機関において国が主導して進めてきた部分にあたる。Helical Fusionは核融合科学研究所からスピンアウトしたスタートアップとして、発電装置の実装を目指している。
「小さな装置で概念的な実証を行い、大型装置を作って1億度のプラズマを実験し、それを一定時間維持する。ここは研究として非常に時間がかかる部分であり、民間ではなかなか手を出せない領域です」(田口氏)
こうした基礎的な成果に目処が立っているヘリカル型を採用することで、「最も不確実性の高いところ以外を完成させれば、発電に届くのではないか」という見通しが得られた。そこでHelical Fusionが取り組むことになったのが、現在地である「工学技術の完成」である。
この段階で鍵となるのが、高温超伝導マグネットとブランケット兼ダイバータの二つの要素だ。高温超伝導マグネットは、プラズマを閉じ込めるための磁力のカゴを作るもので、核融合炉の心臓部とも言われる基幹部品だ。一方のブランケット兼ダイバータは、核融合反応から生じるエネルギーを受け止めて熱に変換し、その熱を用いて発電を行うための「壁」のシステムであり、発電装置として成立させるためには不可欠な技術である。
田口氏は、「この超伝導マグネットとブランケットという二つが揃えば、これまでの成果と組み合わせて、炉の形をした統合的な最終実験装置をつくることができます」と説明する。そこで「全部同時にきちんと動く」ことが確認できれば、あとはスケールを大きくし、出力を上げることで発電につながるはずだというのが同社の見立てだ。
Helical Fusionは、すでに達成された研究の成果を前提に、残された工学的課題に集中することで、2030年代の実用発電を現実的な射程に捉えている。研究と事業の境界線を意識的に引き直し、発電というゴールから逆算して現在地を定めている点に、同社の特徴がある。
最短距離で商業化に向かうための判断軸「ポラリス」と業界連携
Helical Fusionの意思決定を貫く判断軸として、田口氏は「ポラリス」という言葉を用いている。迷ったときに目印となる“北極星”を明確に定め、「最短距離で核融合発電を実現する」ことから逆算して、やるべきこととやらないことを切り分ける基準だ。

この判断軸の根底にあるのは、「寄り道をしない」という強い意思である。研究テーマとしての広がりや派生的な可能性に引きずられるのではなく、あくまで発電というゴールに直結する選択を積み重ねる。その結果として、技術ロードマップも、事業の進め方も一貫した形で設計されてきた。「現在、社員はパートタイムを含めて約40名います。幸いみなさんエンゲージメントが高いのでうまくいっていますが、今後人数が増えていったとしても求心力を失わないようにポラリスを打ち出しているという側面もあります」と田口氏は語る。
しかし、最短距離で進もうとすればするほど、個社の努力だけでは越えられない壁が現れる。その一つが制度・政策の問題だ。核融合発電はエネルギー政策と不可分であり、安全規制や制度設計が整わなければ、技術が成立しても社会実装には至らない。しかも、こうした領域を一社ごとに政府と折衝するやり方には限界がある。
田口氏は「個社でそれぞれ要望を出しても、政府としては受け止めにくいし、我々にとっても効率が悪い」と語る。業界としての共通認識や優先順位を整理し、まとまった形で対話する主体が必要だという問題意識が、次の行動につながった。
その結果として設立されたのが、一般社団法人フュージョンエネルギー産業協議会(J-Fusion)である。J-Fusionは、核融合関連企業が参画し、国との折衝の窓口を一本化すると同時に、民間同士の結束を強めることを目的としている。
J-Fusionの内部には、安全規制の整理や政策提言を担う部会が設けられ、加盟企業の意見を集約したうえで、協議会として政府に提言もする体制が構築されている。実際に、核融合炉の安全確保に関する考え方の土台づくりや社会実装に向けた取組検討などでは、J-Fusionによる政府有識者会議への情報提供や提言も行なっている。
Helical Fusionが業界づくりに踏み出したのは、理想論からではない。商業化という現実的なゴールに向かううえで、「個社では越えられない壁」が明確に見えたからこそ、業界として動くという選択をした。その姿勢もまた、「ポラリス」に導かれた判断の一つだと言える。

小野田内閣府特命担当大臣とJ-Fusion理事企業の意見交換の様子。小野田大臣に向かって右隣がJ-Fusion会長の小西哲之氏(京都フュージョニアリング )、向かって左隣りが副会長の田口昂哉氏。
(J-Fusion HPより https://jfusion.jp/news/2025/1208823/)
IPASを通じて言語化された、経営から逆算する知財戦略
核融合発電という長期的かつ不確実性の高い事業において、知財が重要であることは当初から認識していた。しかし、Helical Fusionでは、IPAS(知財アクセラレーションプログラム)に参加する以前、その知財戦略を経営の言葉として整理しきれていたわけではなかったという。
「知財が大事だという感覚は当然ありましたが、具体的にどう扱うべきなのかは正直あまりわかっていなかったんです」と田口氏は振り返る。技術開発や事業構想は着実に前に進んでいた一方で、知財をどのような位置づけで扱うのかについては、まだ手を付け切れていない部分が残っていた。
転機となったのが、IPASへの参加だった。専門家との対話を重ねるなかで、「知財とは何か」「何を守り、何を出すのか」「その順番をどう設計するのか」といった問いに、経営の視点から向き合うことになった。「特許を取るか取らないか、論文にするか秘匿するかといった個別の判断を、経営戦略からどうバックキャストするかを整理できたのは大きかったです」と田口氏は振り返る。
その結果、Helical Fusionの知財戦略は明確な輪郭を持つようになった。基本は「秘匿」を軸に据えつつ、必要に応じて開示のタイミングと範囲を設計する。知財を特許の数で語るのではなく、「どう考えているか」を一貫したストーリーとして説明できる状態を整えた。
この変化は、資金調達の場面でも意味を持ったという。「投資家からは必ず『知財をどう考えていますか』と聞かれます。そのときに、単に特許の話をするのではなく、経営としてどう設計しているかを説明できると、受け取られ方がまったく違います」と田口氏は話す。実際に、知財戦略を含めて経営全体を見ている点を評価された場面もあった。
IPASを通じて得たのは、知財のノウハウそのもの以上に、「経営と一体で知財を考える視座」だったと言える。核融合発電という未踏の領域に挑むHelical Fusionにとって、知財は守りの手段ではなく、実用発電へと向かう道筋を支える経営基盤の一部となっている。
研究によって切り拓かれてきた核融合の可能性を、どのように社会へつなげていくのか。Helical Fusionは、技術・事業・知財を切り離さずに設計し続けることで、2030年代の実用発電を現実のものとする段階へと歩みを進めている。