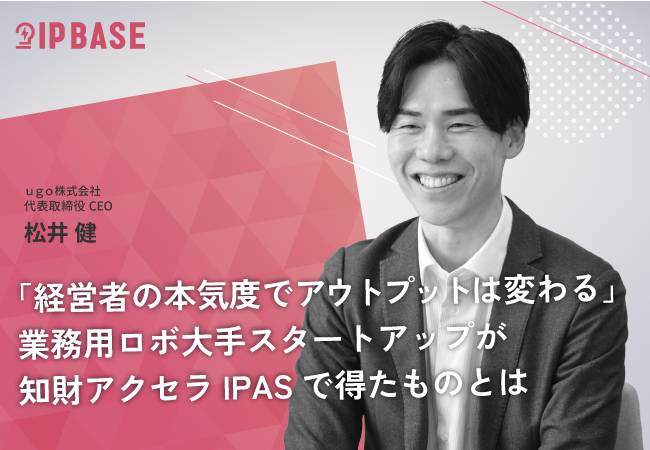CEOが語る知財
エピストラ株式会社 共同創業者 CEO 小澤 陽介氏 インタビュー
知財を生かし、業界パートナーと幅広く連携してバイオ業界全体を支えるプラットフォームをつくりたい
エピストラ株式会社は、バイオ産業における生産性と品質の向上を目指してAIによる自動実験最適化システム「Epistra Accelerate」を提供している。これまで50件以上の研究開発を支援してきた同社は、ライセンスビジネスへの展開に向けた知財強化のため、2022年度の知財のアクセラレーションプログラム「IPAS」に参加。その成果として、2024年には他社との共同開発による細胞培養最適化支援ソフトウェア「CellTune」をリリースするなどしている。同社CEOの小澤陽介氏にIPASへの応募背景とその成果について伺った。

エピストラ株式会社 共同創業者 CEO
小澤 陽介(おざわ・ようすけ)氏
慶應義塾大学でバイオインフォマティクスの学位(博士)を取得後、IBM Researchで研究員を務める。その後、渡英してスタートアップ企業Ecreboの基幹システムと9件の根幹特許を一人で書き上げ、時価総額100億円以上にまで急成長させた。帰国後は産総研技術移転ベンチャーRBI株式会社で実験ロボット「まほろ」の情報システム開発を率いた後、エピストラを創業。数理最適化、データベース、計算生物学分野で原著論文。
バイオ製品の製造を支援するAI自動実験最適化システム「Epistra Accelerate」
近年、がんや遺伝子疾患などの難病治療法として、再生医療やバイオ医薬品が急速に進展している。また、資源の枯渇や食糧問題を背景に、バイオ燃料やバイオプラスチック、培養肉などの研究も進んでおり、バイオ産業は大きな市場になると予想される。しかし、細胞や微生物を用いた生産は制御が難しく、生産コストが高いことが課題だ。エピストラは、バイオ産業の生産性向上や品質向上のためのソリューションとして、AIによる自動実験最適化システム「Epistra Accelerate」を開発、提供している。
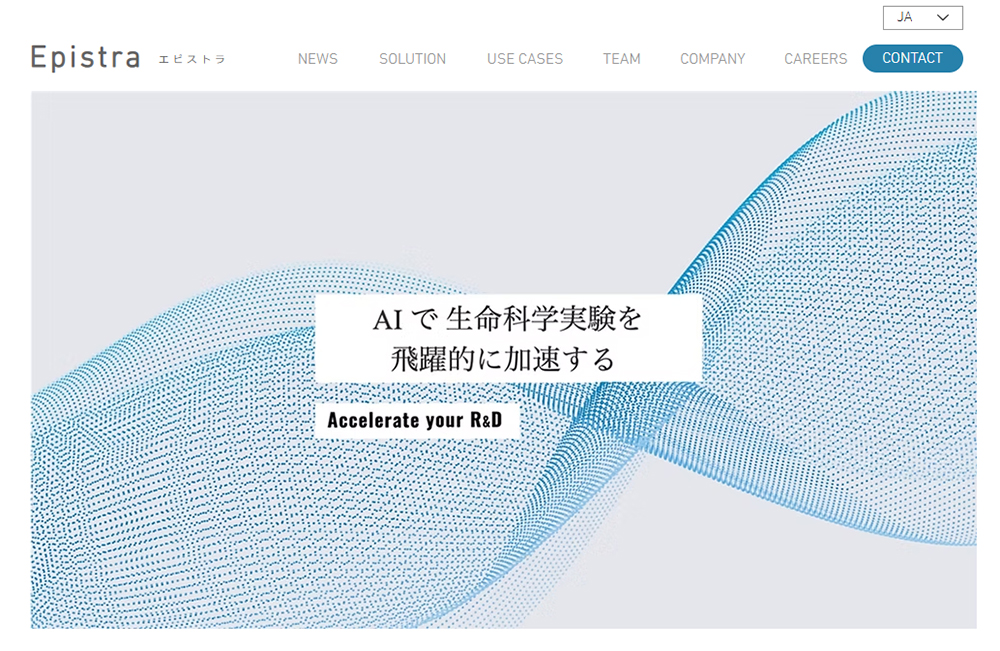
「我々が目指すのは、AIとロボットが自律的に科学を進めて新たな発見をする自律システムです。『Epistra Accelerate』は、独自のアルゴリズムを用いて自動実験と評価を繰り返し、より良い製造条件を探索します。その効果として、生産コストの削減、研究開発期間の短縮が期待できます」と小澤氏は説明する。
現在は「Epistra Accelerate」を用いてライフサイエンス分野の研究開発を支援する「コンサルティングビジネス」と、医療機器メーカー等と連携して製品を共同開発する「ライセンス・プロダクトビジネス」の2つの事業を展開。「コンサルティングビジネス」としては過去4年間で50件以上の生産性改善に貢献し、その実績をもとに今後は「ライセンス・プロダクトビジネス」に軸足を移していく計画だ。2024年9月4日には、株式会社島津製作所との共同開発による細胞培養最適化支援ソフトウェア「CellTune」をリリース。さらに、分析機器メーカーや培養装置メーカーなどとも連携し、バイオ業界全体の効率化と標準化を図っていくという。
IPASで知財化の優先順位を付けられる10項目の評価基準を作成
エピストラは、2022年度の知財アクセラレーションプログラム「IPAS」に参加した。まず、応募したきっかけについて伺った。
「IBMの研究室に勤めていた当時、業務として日常的に特許についても携わっていたので、知財には馴染みがありました。知財の重要性をより強く実感したのは、その後の英国のスタートアップ(Ecrebo)での経験です。特許を取ったことで資金調達や提携が有利に働きました」と小澤氏。
ただし、Ecreboでは小売店向けのビジネスで大きな利益を出てから特許を出願しており、守るべきアイデアが明確で資金にも余裕があった。
「エピストラでは、そのような大きな資金があるわけではありません。特許になりそうなアイデアはたくさん思いつくものの、知財に使える資金や人的リソースも限られている。そこで、事業との整合性を持った形で、どのアイデアを知財化していくかの優先順位をつけたかったのがIPASに応募した理由です」(小澤氏)

「ライセンス・プロダクトビジネス」を成長させていくには知財戦略が重要になるという。そこでIPASでは、知財化の優先順位をつけるための評価基準の設計に取り組んだ。作成した評価基準は「コンサルティングビジネス」と「ライセンス・プロダクトビジネス」の2軸で、1)対価を払う根拠性、2)物理的な強さ、3)ライセンス契約を続ける根拠になり得るか、4)実施の容易さ、5)単願か共願か――の各5項目、合計10項目で技術やアイデアを評価するものだ。
「この10項目を基本として評価し、成績のいいものを優先的に知財化していけばいい。特許出願や知財の活用に関する判断がスムーズになり、知財関連業務の効率が上がりました。事業との関連性が高い知財や他社との差異化につながる知財を優先的に確保できるようになったことも成果です」
開発においても、知財化の優先度に応じて事業と関連性の高い技術にリソースを集中できるようになったメリットがあるという。
知財はダイエットと同じ。効果はすぐには見えないが、ペナルティはあとからやってくる
次に、これから知財活動に取り組む起業家へのアドバイスを聞いた。

「ある条件を満たしたら、できるだけ早く知財に取り組むことをおすすめします。“ある条件を満たしたら”というのは、事業の見通しがあまりに不確実なうちに特許を取ってもあまり意味はないと思うからです。事業アイデアが具体化し、独自技術が確立したら、知財に関する取り組みを始めるといいのではないかと思います。
スタートアップはリソースの制限などの理由から、知財が後回しになりがちです。しかし、知財はダイエットと同じで、目に見える効果がすぐに出てくるわけではありません。だからといって取り組みを後回しにしたままだと、ペナルティは後からやってきます。特許は先願主義なので、後から取り返しはつかないので、条件を満たしたら早く手を付けることが大事です」と小澤氏。
また、知財活動をうまく進めるには、信頼できる専門家を見つけることも大切だという。創業メンバーに知財に詳しい人がいたとしても、知財戦略や契約に関しては専門家を頼ることをすすめている。エピストラの場合、小澤氏は知財、COOの櫻田剛史氏は法務に詳しいが、IPASのメンターからAIソフトウェアなどに強みを持つ弁護士を紹介してもらい、共同開発やライセンス契約のサポートを受けているそうだ。
「知財戦略や契約に関する知識は、専門家にはかないません。独自に進めようとすると、意図した権利の確保が難しくなる場合があります。我々も大手企業との契約の際、専門家のアドバイスを受けることで、契約内容をより実現可能な形に調整し、双方にとって適切な合意を形成することができました。専門家の力を借りることで、契約として成立し、かつ事業の成長に必要な権利を確保できるバランスの取れた契約を結ぶことができます」と小澤氏。
問題はどうやって信頼できる専門家を見つけるか。起業家仲間やVCなど信頼できる相手から紹介してもらうか、IPASなどの伴走支援を活用してみるのもいいかもしれない。
最後に、今後の事業展開について小澤氏に伺った。
「短期的には、今持っている知財をベースにして、ライセンス事業やリカーリング事業などスケールする事業をさらに伸ばしていくこと。そして長期的には、高品質なバイオ製品をリーズナブルに大量生産できるようにしたい。その観点でいえば、現在の我々のソリューションはひとつの要素でしかない。分析機器メーカーや培養装置メーカー、CDMO(医薬品開発製造受託機関)といったあらゆる業界パートナーと連携しながら、バイオの研究開発をサービス化し、バイオ業界全体の効率化と標準化を図るプラットフォームを構築するのがゴールです」